前回は骨折から回復し、出勤を再開したり、普通の靴を履けるようになったり、という変化について書きました。

骨折から手術、リハビリ、そして通勤再開と、少しずつ日常生活を取り戻してきました。この数ヶ月間、アメリカの医療制度の中で治療を受け、改めて 「日本とは大きく違う」 ということを実感しました。
特に、アメリカでは 「病院は手術まで」「回復は自分で」 というスタンスが基本。
また、リハビリは私のような骨折の場合、一般的に術後6週間後から開始し、その後も「6週間ごとの診察を受けながら、段階的に回復していく」 というシステムです。
今回の骨折・手術・リハビリを通じて、 アメリカの医療の仕組み、PTの重要性、そして日本との違い を実感したので、改めてまとめてみようと思います。
アメリカの医療制度は「分業制」
アメリカの医療の特徴のひとつに、「病院だけですべてが完結しない」ことがあります。
診察・手術・リハビリ・薬の処方…すべて異なる施設に分かれており、各専門分野ごとに別々の機関で対応するのが一般的です。
🏥 病院(Hospital) → 診察・手術を行う場所
🦵 PT(Physical Therapy:理学療法) → リハビリを専門にする施設
💊 薬局(Pharmacy) → 処方箋をもとに薬を受け取る
私も手術後、 入院なしでそのまま帰宅し、自宅で安静にしていました。術後6週間は「非荷重(足を床につけてはいけない)」期間となり、その間は リハビリも受けられない というのがアメリカの標準的な流れ。
日本では病院内でリハビリを受けるケースも多いですが、アメリカでは「病院=治療をする場所」「リハビリ=PTで行うもの」と完全に分業されています。リハビリの頻度や期間は 医師からのRefferalというもので定められています。患者はこれを持って、自分の加入する医療保険のネットワーク内のPTを探して受診するという仕組みです。
ㅤ
また、手術する病院と医師の勤務する病院が同じ建物とは限らず、私の場合は同じ系列の病院でしたが、両者は車で20分くらい離れた距離に位置していました。そのため、手術先の病院に行ったのは手術当日だけです。
入口は医師の紹介状
さて、アメリカでリハビリをやるのは前述ではなく、PT(リハビリ専門の施設)です。骨折や捻挫等の患者は、 「リハビリが必要」 という診断を医師から受けた後、 「Referral(紹介状)」 をもらいます。Referral には、以下のような内容が記載されます。
🔹 患者の状態(骨折後、手術後など)
🔹 リハビリの目的(歩行回復、関節の可動域改善など)
🔹 リハビリの回数(例:週2回・6週間)
🔹 リハビリの強度や制限(例:最初は非荷重、徐々に荷重OK)
このReferralがないと、基本的に PTは保険適用にならない ため、事前に必ず医師の診察を受ける必要があります。
PTでやること
PTの初回訪問では、まず セラピストが詳細な評価を行い、リハビリプランを作成 します。
Referralの指示に基づきながら、患者の状態を確認し、具体的なリハビリメニューを決めていきます。
🔹 可動域(Range of Motion)のチェック → 足首や膝がどこまで動くか?
🔹 筋力の評価 → どれくらいの負荷をかけられるか?
🔹 痛みのレベルの確認 → どの動作で痛みを感じるか?
🔹 歩行の状態の確認 → 松葉杖・ブーツ・裸足でのバランスチェック
この診察をもとに、 「何週間でどこまで回復させるか?」 という目標を立て、リハビリメニューを決定します。
PTの頻度は 週2〜3回程度が一般的 ですが、保険の種類によって適用される回数が決まっています。
たとえば、ある保険プランでは 「週2回 × 6週間(計12回)」 というように、期間が設定されていることが多いです。
🔹 PTで行う主なトレーニング
✅ ストレッチ(関節の可動域を広げる)
✅ マッサージ(浮腫みや硬さをとる)
✅ 歩行練習(松葉杖 → 杖なしへ移行)
✅ 筋力トレーニング(足の筋力を戻す)
✅ バランストレーニング(足首の安定性を取り戻す)
リハビリを進めながら、 6週間ごとに医師の診察を受け、経過を確認しながらリハビリのプランを調整していきます。
私の場合、特に 「階段の降り方」 は、自己流では怖かった部分。荷重開始初日にPTでコツを教えてもらうことで、それまで厳禁だと思っていた「階段」への抵抗が薄まりました(地下鉄など)。
PT(理学療法)では、専属のセラピストが担当として決まり、通常はその人とアポイントを取って通います。私が通っていた施設では、1回の施術は約40分間。その中で、流れは大きく 前半20分・後半20分 に分かれていました。
🔹 前半20分 → 専属セラピストによる施術
・マッサージによる柔軟性回復
・必要なトレーニングの指示と指導
🔹 後半20分 → アシスタントに交代
・セラピストが指示したメニューの実践
このように最初に専門的な施術を受けた後、実践トレーニングに移る、という流れです。
このシステムは、リハビリの質を保ちつつ、PTの効率を上げるためのもの。セラピストの人達は何人もの患者さんを抱えているので、私が行く時はいつも前後に違う人が来ており、とても忙しそうでした。患者は年配の方が多い印象はありましたが、若い働き盛りの方、マッチョな男性などもチラホラ。エリアにも寄りますが、日本の整形外科よりは若い人が多めかもしれません。
選ぶならIn-Networkの医療機関?
アメリカの医療費は 「世界でも有数の高額水準」 と言われるほど。だからこそ、保険が適用される範囲を事前にしっかり確認することがとても大切です。
ㅤ
まず、アメリカの医療保険では、In-Network(ネットワーク内の医療機関)とOut-of-Network(ネットワーク外の医療機関)の概念が重要です。
🔹 In-Network vs. Out-of-Network
In-Network(ネットワーク内)の病院で手術を受けた場合、保険会社が契約している医療機関のため、費用は一定の割合でカバーされます。
Out-of-Network(ネットワーク外)の病院で手術を受けると、保険適用外または部分的な適用となり、自己負担額が大幅に増える可能性があります。
ㅤ
そのため、手術を受ける前には、医療機関が自分の保険のIn-Networkかどうかを確認することが必須です。
🔹 自己負担の上限と払い戻し手続き
個人が加入している医療保険のプランによっては、自己負担の上限額(Out-of-Pocket Maximum)が設定されています。例えば、「自己負担上限:5,000ドル」というプランであれば、それ以上の医療費は保険会社が100%負担する仕組みです。
また、一部のプランでは、Out-of-Networkの病院で受けた治療についても、一部払い戻しが可能なケースがあります。ただし、払い戻しには手続きが必要であり、全額がカバーされるわけではないため、事前に保険会社に確認しておくことが重要です。
何にいくらかかった?
以下に今回支払った各項目と費用について書きます。
🔹 手術費用
一般的に高額で全て合わせると通常1万ドルを軽く超える。保険適用後でも、数百〜数千ドルの自己負担が発生する。ちなみに一言で「手術」といっても麻酔費用、執刀医の施術費用、施設使用のための費用、手術当日のPT指導に係る費用など複数項目に渡り、請求が届く。
🔹 PT(リハビリ)
(私の通うPTの場合)上述の自己負担額上限に達するまでは、1回あたり 約350ドル前後(保険適用後の自己負担額はプラン次第)。
🔹 松葉杖・車椅子等の器具
意外とリーズナブルで松葉杖は$50~$60前後、車椅子は$150~$200前後。その他私はニースクーター(膝を乗せて使う医療用スクーター)を活用していましたが、$100程度。松葉杖はドラッグストアで購入しましたが、他はAmazonで購入しました。
私の場合、手術が11月で既にある程度の自己負担額をこれまで支払い済みであったことと、医療保険 のIn-Networkの病院に受診・手術を受けたため、ある程度の金額を支払った時点で自己負担額上限に達し、その後は医療費が100%保険会社負担でした。ただし、この自己負担のカウントは1/1~12/31のカレンダーイヤーのため、その恩恵を受けられたのも12月の1ヶ月間だけでした(1月1日に再度リセットされたため)…。
ㅤ
ちなみに、もしこうした現地の保険がない場合、手術費用だけで数万ドル単位の立替をしなければなりませんでした。
特に旅行などでアメリカを訪れる際は、「海外旅行保険」の加入を絶対に忘れないように!なぜなら、保険を持っていない場合、「全額自己負担」が原則。ちょっとした怪我や病気でも 数百〜数千ドルの請求が発生、手術に至っては数万ドルに達するので、保険なしでの医療費負担はかなりの痛手です!
ㅤ
ㅤ
次回はいよいよ 骨折シリーズの最終回(予定)。ここまでの経験を振り返りながら、骨折を通して学んだことや、リハビリを経て感じた変化についてまとめたいと思います。
注:1ドル=約151円(2025年3月3日現在)
ㅤ
ㅤ
3/9(日)スタート!「伝わる!スピーチDojo(第3期)」↓



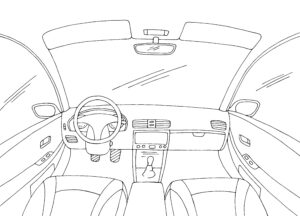
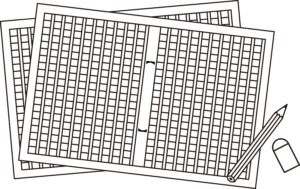



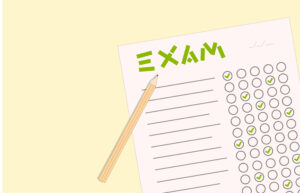


コメント